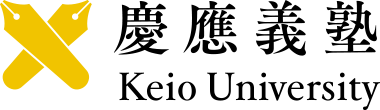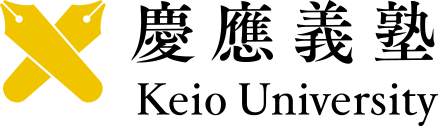ヘッダーの始まり
審査結果
本文の始まり
第50回小論文コンテスト審査結果
課題
1.わかりやすさ
2.2050年のわたしと国際社会
3.福澤諭吉の演説
4.選挙とSNS
5.AIと人権
6.自由課題(関心を持っている事柄や問題について、自由に課題を設定してください)
応募総数
299篇
受賞者
作品名をクリックすると作品のPDFが見られます。
【小泉信三賞】
問山 遼太郎(といやま りょうたろう)京都府/京都市立紫野高等学校2年
【選択課題:1】
「『公平なスタートライン』としてのわかりやすさ-ディスレクシアと学びの多様性」
【次席】
明樂 和磨(あきら かずま)茨城県/私立S高等学校2年
【選択課題:5】
「AIは人権を『完成』させるのか~『全知の無知』と倫理のマクドナルド化~」
【佳作】(五十音順)
安藤 千紘(あんどう ちひろ)愛知県/私立聖霊高等学校2年
【選択課題:2】
「環境問題解決への糸口をつかむ-国際社会をつくる『わたしの集合体』」
坂 綾高(さか あやたか)山梨県/私立山梨学院高等学校2年
【選択課題:2】
「バナナの沈黙-加速社会に抗う哲学的抵抗」
竹縄 智(たけなわ さと)東京都/私立女子学院高等学校2年
【選択課題:2】
「誰もが音楽を楽しめる社会にするために-音楽と政治は別物と考えるべき?」
原 夏希(はら なつき)(東京都/私立広尾学園小石川高等学校1年)
【選択課題:4】
「『熟議』を問い直す-SNS時代の選挙と政治参加」
日垣 朋果(ひがき ともか)神奈川県/私立中央大学附属横浜高等学校2年
【選択課題:1】
「『わかりやすさ』のその先」
最終選考進出者(受賞者を除く)は以下からご確認ください。
最終選考進出者
審査委員(五十音順) 選評
小川原正道(慶應義塾大学 法学部教授)
恋田 知子(慶應義塾大学 文学部教授)
小西 祥文(慶應義塾大学 経済学部教授)
谷口 和弘(慶應義塾大学 商学部教授)
早川 浩(株式会社早川書房 代表取締役会長)
町田 智子(公益財団法人文字・活字文化推進機構 専務理事)
第50回小論文コンテスト受賞者の声
受賞者の声の一部を紹介します(編集:慶應義塾広報室)
受賞者の声
日頃から考えていることを、思いつきのままに終わらせず、きちんと文章として残してみたいと思い、応募しました。テーマを決めようとして真剣に考えれば考えるほど、かえって何も決まらない時間が増えていきましたが、振り返ってみると、その迷っている時間こそが、自分の考えを一番深くしていたことに気づきました。そこで、その「一見意味のないように思えても、実は重要な時間」自体をテーマにしようと思い、「間」を選びました。今回の受賞に関して、文章を書くことは楽しい反面、自分の考えの浅さを何度も突きつけられる作業でもありました。それでも、すぐに答えを出さず、寄り道しながら考える時間は決して無駄ではないと分かったので、今後もあえてその「効率の悪さ」を手放さずにいたいと思っています。
(選択課題:2050年のわたしと国際社会)
自分自身が当事者であり、様々な経験を通して、ディスレクシアについてもっと知ってほしいと思っていました。そのような中で、塾の先生が勧めてくださったことがきっかけで応募しました。この小論文コンテストについて調べた時に、1番最初に「わかりやすさ」というテーマが目に飛び込んできました。自分自身、これまでずっと「自分らしい学び」を考えてきたので、迷いなく選択しました。
今、私は高校生活を勉強面も含めて心から楽しんでいます。この小論文を通して、ディスレクシアという個性を持ちながらも、自分にあった学び方を見つけたら、楽しい学校生活を送れることを知って、ディスレクシアというものを理解してくださる方が増えたらうれしいです。これまで私に関わってくださった学校の先生や、家族、仲間たちに感謝しています。
(選択課題:わかりやすさ)
高校の国語の授業でいくつかの文芸コンテストが紹介されたのですが、貴コンテストの6000字から8000字という規定字数の多さが印象に残りました。そのため、自分が興味をもっている分野について知見をより深められるのではないかと考え、応募に至りました。
この受賞は私に言葉の重みについて考えるきっかけを与えてくれました。今回、自分の「好きなもの」を主軸にして小論文を書いたため、論旨とは全く異なるネガティブな意味合いでの自分の主観が含まれてしまっているのではないか、と逡巡してしまいました。
また己の未熟さ故に正確さや倫理性に欠けた文章を造り上げてしまったのではないかと不安に思い(今も思っているのですが)これこそが言葉の重み、責任なのだなと感じました。
この重みに高校生のうちから気がつくことができたことはとても幸せなことだと思います。
(選択課題:2050年のわたしと国際社会)
小論文を書く練習になればと思い応募しました。歴史あるコンテストで、課題も考えがいのあるものが多かったので、自分の考えを整理する良い機会になると感じました。
私の学校では授業で生成AIを使う機会があり、自分自身も日常的にAIを利用しています。
その中で、便利さに頼りすぎてしまう場面や、AIの回答をそのまま受け入れてしまいそうになる自分に違和感を覚えることがありました。その経験から「AIと人権」という課題に関心を持ちました。
今回の受賞については、問題の指摘はできても、解決策の提案が弱くなってしまったという自覚があったので、次席をいただけたことは驚きでした。自分なりに考え、論を組み立ててきたことが少し認められたような気がして、励みになりました。
(選択課題:AIと人権)
慶應義塾大学を志望しており、志望大学の主催するコンテストであることから、挑戦することを決めました。また、昨年度受賞できずに悔しい思いをした経験から、リベンジしたいという思いもありました。昨年度は「真実」のテーマを選択し、安倍総理銃撃事件を題材に小論文を執筆しましたが、自身の経験と十分に結びつけて論じることが難しいと感じました。そこで本年度の応募に際しては、より自分の経験を起点に考察できるテーマを探しました。その過程で、自身の興味分野である舞台衣装が、「わかりやすさ」というテーマと深く関連していることに気づき、本課題を選択しました。
今回の受賞は、これまで自分の中で言語化しきれなかった違和感や問いが、ひとつの形として受け止められた経験でした。また、自身の問いに向き合い続けてきた姿勢を後押ししてくれるものでもありました。この経験によって得た自信を糧に、新たな探究にも着手しています。今後も、表現と社会をつなぐ視点から、探究をさらに発展させていきたいです。
(選択課題:わかりやすさ)
学校の教員からコンテストを勧められた際、課題2の「2050年」を見て2050年間題のことが頭をよぎり、環境問題を中心に自分の考えを文章にしてみたいと強く思ったため、応募しました。人間と地球の双方にとって明るい未来を迎えるために、国際社会の在り方を2025年の今に考えるべきだと思いました。
今回の受賞を通じて、これから小論文を読んでくださるより多くの人に、環境問題解決のために自分が必要だと考えた力を共有できると思いました。
自分の作品を佳作に選んでいただいて、素直に嬉しいです。小論文を通して伝えたいことを伝えられたように感じ、自信に繋がりました。
(選択課題:2050年のわたしと国際社会)
昨今のインターネットでの政治的議論をみていて、政治とSNS、そして熟議について考えることがあり、たまたま今年の課題テーマの中に「SNSと選挙」というものがあったため、これを機に自分の思考を整理し、ファクトと共に文字にしてみるのも良いかもしれないと思い応募しました。
私にとって、高校生である今の時間を興味深いテーマについて多くの本を読み研究し、自分の思想や考え方を整理して文字に起こすことに使うことは、自分の人間的成長という意味でも非常に価値があると思いました。また、若者である自分の視点から語られる熟議やSNSと政治に関する声がこのように多くの人に渡るということはなかなかないと思うため、今回の受賞を通じ、自分の文章が大人に認めてもらえるものなのだと自信にも繋がりました。
(選択課題:選挙とSNS)
関連コンテンツ
サイトマップの始まり