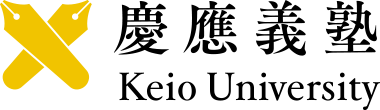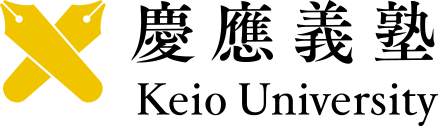ヘッダーの始まり
- ホーム
- 教育
- 一貫教育校(小・中・高等学校)
- 慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉
-
志木高の豊かな自然を用いた教育
志木高の豊かな自然を用いた教育
慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉
慶應義塾一貫教育校の自然教育
(2024年9月掲載)
志木高の豊かな自然を用いた教育
宮橋裕司さん
志木高等学校教諭(生物・地学)
志木高は約10万平米という広大な敷地の約4、5割が樹木に覆われた森林となっていて、まさに武蔵野の雑木林の里山風景が残っている自然環境です。1995年、私が志木高に着任し、はじめてこの森を歩いてみた時、これだけ多様な樹木・植物の層を抱えていることに驚き、とても大きな財産だと思いました。
志木高内には植物の種類が約600種弱が確認されていて、その分厚い植物の層が下支えになって様々な昆虫が生活しています。私もここに来て初めて「生きて飛んでいる玉虫」を見ました。他にもクワガタ、カブトムシ、ナナフシは普通にいますし、蝶で言えばアオスジアゲハ、アサギマダラなども見かけることができます。野鳥の数も多く、20数種類。防火用水のところではほぼ毎年、カルガモが子育てをし、時にはオオタカが狩りをする様子も見ることができます。
 カブトムシ
カブトムシ カルガモの雛
カルガモの雛この森の豊かさをどのように生徒の教育に使えるのか、自然への意識を生徒にもってもらうために学校全体への情報発信が必要だという思いから、2002年に「四季――自然報告」(B4裏表、二つ折)という小冊子の編集・発行を始めました。
当初から理科の教員だけでなく、幅広い分野の先生を巻き込み、切り口を多様にすることを編集方針としました。教員室での雑談の中から、俳人として著名な国語科の先生などに、生物以外の着眼点でふくらみを持つ寄稿をお願いしました。
教員も社会科や国語科の先生からも様々な反応があり、教員同士でのコミュニケーションツールとしても役立っているようです。実際に国語の授業に私がお邪魔をして、方丈記に出てくる地震(「なゐ」)、が理科年表にきちんと記録されている史実であることを話したりする、文学と理科の融合のような試みもしてきました。現在は実験助手の方に編集長を任せ、寄稿をお願いした先生方には前向きに協力していただけています。
 志木高全景(航空写真)
志木高全景(航空写真)志木の自然の最大の魅力はその生物多様性がとても豊かであることだと思います。例えば、校舎新築にあたり仮設校舎のために大規模な伐採を行うと、そこから立ち直るために、自然が再構築されていきます。予測がつかない再構築があるのも、これはその大もとに豊かな自然、多様なベースがあるからこそ可能なのだと感じます。一度更地にしたところに何の植物が生えていくかを見るのはとても興味深いものです。数多くの樹木、草花があるがゆえに鳥のフンで種が蒔かれたり、人の移動で種子があちこちに運ばれたり、といったことが日常的に起こっているわけです。種子散布の補助手段自体が学校の中にあるのです。
そして、このような豊かな変化を生徒たちが日々見られることが学校の自然から受ける最大の恩恵です。ある時にたまたま見た一瞬ではなく,日々起こっている小さな変化を生徒が見続けられることが財産です。本校の生物部は現在2、30人の部員がいて、コロナ後にその数は着実に増えているように感じます。彼らは普段から学校の中を毎日歩いているので、この変化を常に見ていると思います。昆虫好きの生物部員の中でも、植物や昆虫に対して多様な嗜好を持つ子もいて、生徒同士が互いに刺激を受け合うような環境は醸成されてきていると思います。
私自身、もともとあまり文系、理系といった分け方に納得していない部分があり、理科の教育にも民話や伝承をもとに考える授業などを取り入れてきました。学校教育を受ける前の段階の人が、科学に対してどんな興味をもっているのかを調べたことがあり、その手がかりとして民話を使いました。例えば、今、熊による被害が全国で多く出ていますが、その多くは柿のような果樹を求めて人里に出たものです。全国の民話の中には熟れた柿をもがずに無駄にしたことを戒めるような妖怪が出てくる話が結構あります。これは直接熊が出てくる話ではないですが、何か自然からの警鐘という意味でつながっているようにも感じられ、こういった民話を採り入れた理科の授業は、文系の生徒も関心をもって聞いてくれているようです。また、フランス革命などの史実に触れるときも、その原因を失政ではなく、前年に噴火したアイスランドの火山噴火にともなう農作物の不作に求める、といった視点の切り替えも伝えています。 志木高で様々に行われている自然を題材にした教育の取り組みは、いわば学習指導要領で規定された枠組みを取り払い、自由な視点で、物事に接していく教科をクロスオーバーして教える試みとも言えると思います。慶應では枠にはまる必要はありません。特に大学では既成枠に囚われず、自ら新たな枠組みを作ることを求められます。
卒業生は、久し振りに志木高に来ると森の中を歩きたくなるようです。日常から離れた雰囲気は、在校中はほとんど当たり前ですが、卒業すると、いかに恵まれた環境であるか、その良さに気付くことが多いようです。森の中を歩いていると喧噪から隔絶された感じで安心感を与えてくれます。また、近隣の住民の方々に向けて「自然観察会」を春秋の2回開催しており、自然に触れていただくとともに、学校のことをよく知っていただくよい機会にもなっています。
 自然観察会の様子
自然観察会の様子近年、木々の樹高がどんどん高くなり、より計画的な植栽管理が必要になってきています。この志木の環境は「気が付いたらそこにある」というのが多くの人の印象だと思います。教職員、志木高生、卒業生にとって潜在意識下にあるこの森を意識して、どのようにこの森を守り育てていくかを考える必要があるように感じています。
サイトマップの始まり