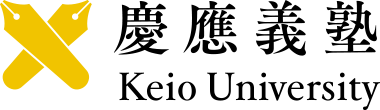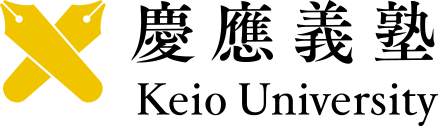ヘッダーの始まり
- ホーム
- 教育
- 一貫教育校(小・中・高等学校)
- 慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉
-
普通部の森づくりと自然観察
普通部の森づくりと自然観察
慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉
慶應義塾一貫教育校の自然教育
(2024年9月掲載)
普通部の森づくりと自然観察
有川智己さん
経済学部教授、普通部講師

選択授業である「普通部の森」の授業は2001年頃から始まっています。私は2004年に慶應義塾大学の助手(嘱託)として初めて日吉に来たのですが、その頃から、普通部の森の授業に関わっており、もう20年になります。授業内容を一言で言うならば、蝮谷の斜面林(雑木林)の自然回復作業です。つまり雑木林の下草刈り、枝打ち、あるいは枯れた木があればクヌギ、エゴノキなどを植樹するなど、雑木林の管理をしながら、自然観察をする授業で、毎週土曜日に2時間森に足を運んでいます。
授業には、毎年必ず昆虫好き、自然好きの子が一定割合含まれていて、そういう生徒たちはとてもこの授業を楽しみにしてるようです。最初は皆、やはりこの森が想像を超えて大きく広くて、「森なんだ」という驚きを持って感じるようです。森にまったく慣れていない生徒も徐々に森に慣れていき、虫が最初は触れなかった生徒が触れるようになったりします。
室内での座学や実験・観察ではなく、森の中で2時間ほど体を動かす中で、いろいろなことが生徒に身に付いていくことは実感します。下草を刈り、横枝を刈る。立っている木を切ったりもする。これを繰り返すと授業の後半はへとへとになります。枝や下草を刈ることを体で覚えていくということは、自然を学ぶにはとても大事なことで、それも毎週、季節の変化がある中で継続して行うのは得難い経験だと思います。生徒たちは毎週それをやることで植物の変化のスピードが実感としてわかります。草刈りとの競争のような感じの中で草の成長や植物の入れ替わりの早さを実感します。
生徒同士が学び合うこともあるようです。例えば昆虫に興味が特化していた子が植物やきのこ好きの子の話に触れることで興味の幅が広がります。当初、マニアックな昆虫好きの子と距離をおいていた普通の子が、毎週一緒に過ごしているうちに、それが当たり前になって馴染んでいくところもあります。
 「普通部の森」の授業の様子
「普通部の森」の授業の様子また、普通部から塾高、大学の生物学教室へとつながる慶應の一貫教育校ならではの良さも感じます。今年の私の大学の授業には普通部の授業を受けていた人がいます。初回授業の日に4年も前の普通部の時に毎週提出してもらっていたノートを見せてくれました。こういうところにつながりが上手くできていると感じます。また卒業生にとって、普通部の授業で植えた木に大学生になって出会えることはとても有意義なことです。なかには森の管理をする「公認学生団体uniぼらんて」に加わって草刈に来てくれたりします。皆でこの日吉の森を育てているのです。
2002年から苗木を植えているので、「君たちの先輩が植えた木だよ」と見せることもできます。継続してきたからこその驚きがあり、また、20年前、10年前と比較しながら、森がどのように出来ているのかも考えることができます。また、継続してきたことで、森自体がいかに変わるかがわかり、それを教育にフィードバックできています。荒れた状態から回復がなされ、今、かなり感じの良い雑木林が部分的にはできています。
中学生は大学生の冷めた感じとは全く違って反応がダイレクトで面白いと感じます。これは大学教員だけをやっていると得られない体験でもあり、自分もとても勉強になっています。今、大学生は森のことはほとんど知らないので、今後、大学全体に日吉の森の豊かさの意義が広がっていけばよいと思います。
少し心配なのは、クヌギやコナラの老木、巨木がこの3年ほどでナラ枯れにあい、荒れている場所もあることです。しかし、そういったことも含めて自然の現象として学ぶことも貴重なことです。日常の授業で、そういうことを実地で学べるのはとても有り難いことです。日本の林業や里山のあり方についても語れる場として日吉の森はあるのです。
サイトマップの始まり