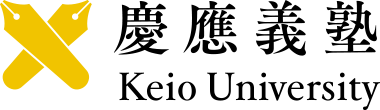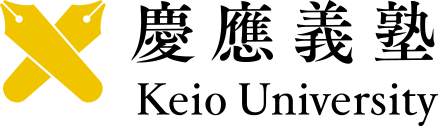ヘッダーの始まり
- ホーム
- 教育
- 一貫教育校(小・中・高等学校)
- 慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉
-
慶應義塾高等学校の森を保全する生徒会活動
慶應義塾高等学校の森を保全する生徒会活動
慶應義塾の一貫教育〈同一の中の多様〉
慶應義塾一貫教育校の自然教育
(2024年9月掲載)
慶應義塾高等学校の森を保全する生徒会活動
串 悠翼さん 高等学校教諭
綿貫暁文さん 高等学校2年在学中
鈴木大惺さん 高等学校2年在学中
 作業中の環境福祉委員会
作業中の環境福祉委員会綿貫さん・鈴木さん:生徒会の環境福祉委員会では森の自然回復・整備の活動を行っています。中心メンバーは5人です。コロナ以降、あまり活動ができなくなってしまっていたのですが、先頃ようやく再開したところです。作業内容の引継ぎがされていなかったので、一からやっていこうと、日頃、日吉キャンパスの整備をしてくださっている東急グリーンさんにお願いして、鎌の正しい使い方などを指導してもらいました。また植えた苗のまわりにある雑草の除去などをしました。森の中の草で危ないものなども教えてもらいました。福山欣司先生(慶應義塾大学名誉教授【経済学部】)からも蜂が多くて注意する場所など細かいことを教えてもらいました。コロナの間にだいぶ森が荒れてしまっていたので、人が歩くことができる遊歩道も整備したいと思っています。
日吉の森は、普通部生の時に理科の「フィールドノート」の課題で行ったのが最初です。その時はシダ植物のスケッチをしましたが、意識して見ると色々な種類があること、一つの植物としてより生き長らえるための姿に感動しました。また、日吉は街なのに学校の中にこんな森があるんだと驚き、生態系がきちんとそこにあることが意外でした。少し調べると日吉の街が開発される以前は街全体が雑木林で里山が守られていたのですが、開発されてそれがなくなってしまったのです。しかし、森は日吉キャンパスの中にはきちんと残っています。
この今でも学生と森が共存している、その環境がとても貴重だなと思います。それが現在、コロナの時期に手を入れていなかったこともあり、森は一部にナラ枯れも起きてしまっています。わずか2、3年の間でも自然の変化のスピードはすさまじいと感じます。
 作業後の森の様子
作業後の森の様子日吉の森の歴史については福山先生から何度もお話しをきかせていただきました。私も大学の活動(uniぼらんての活動)に参加したこともあります。
森の中には珍しい植物もあります。その場所の手入れが行き届いていなくて、これはどうにかしていかないといけないと思っています。植物の生長の速度は速いのでちゃんと手入れをやっていないと、あるはずのものもなくなってしまうと思います。それもキャンパスの中に森があるからこそ気付けることです。
塾高の他の皆にも森の整備に参加しようという呼びかけをしています。また、ユニボラの方に伺っても、一貫教育校から活動していた人たちが多いので、他の義塾一貫教育校全体で森の保全に取り組めば、つながりももてるし、環境を守ることにもつながるのではないかと思います。
![蝮谷、テニスコート付近から臨む(昭和27年撮影、提供:林田新一郎様[6期])](img/interview03_04.jpg) 蝮谷、テニスコート付近から臨む
蝮谷、テニスコート付近から臨む(昭和27年撮影、提供:林田新一郎様[6期])
これは昭和27年、戦後植林をする前、蝮谷がはげ山だった頃のもので、串先生によれば、塾高のアーカイブ委員会に卒業生から寄贈されたアルバムの写真だとのことです。ここから植林をして大きな森が育っていたかと思うと驚きを感じます。このキャンパスの中で新しい風景を作りたいです。きちんと雑木林を管理し、想像つかないような景色、ちょっと足を踏み入れたら珍しい植物があるような、ふっと入ったら心安らげるような場所ができればと思います。
正直、高校生の生徒会の組織で管理するのは大変な部分もあると感じています。植物も繁茂し過ぎてどうにもならなくなっているところもあります。オオスズメバチの女王蜂もいたりするのです。また笹がすごく多くて、非常に断面が鋭利で切れ味が多くて踏んでしまうと危ない。慶應義塾全体で絶対必要な森なので、大人の方も含めて、皆で協力し合って守っていくことができたならと思います。
きちんとした整備を経て塾生が気軽に立ち寄り、自然に触れながらいろいろな考え事ができる場所として、街の中、キャンパスの中に残っていることがとても大切だと思います。その森を守り、より素敵な場所にしたいと思っています。
串先生:生徒が非常に熱心な活動をしているので、教員は生徒がやりたいことに対して支援していくだけです。まだようやく再開したばかりなので、これからしっかり定期的に活動していくと思います。人手不足が一番大きな課題で、特に虫が嫌いゆえに参加してくれないということが非常に多い。何とか虫嫌いの子たちが参加してくれる仕組みを整えたいと思っています。
サイトマップの始まり