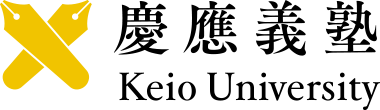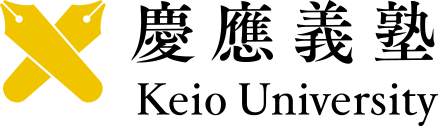ヘッダーの始まり
- ホーム
- Keio Times(特集)一覧
- Keio Times(特集)
本文の始まり
あの日、あの時、4Kでよみがえる戦後の慶應義塾
2025/09/30
慶應義塾は1858(安政5)年に福澤諭吉が築地鉄砲洲で開いた蘭学塾を始まりとし、2025年で創立167年を迎えました。幕末維新という激動の時代に生まれた学塾は、福澤が門下生たちに託した「慶應義塾の目的」を受け継ぎ、令和の現在もなお未来を見据え、発展を続けています。
広報室では2033年に来たる創立175年に向け、広報用画像や映像のデジタルアーカイブ化を進めています。映像の一部は4Kデジタル化し、今春より、「あの日、あの時、映像でよみがえる慶應義塾」シリーズとして慶應義塾公式YouTubeで公開をスタートしました。
このシリーズは、戦後の慶應義塾を映した記録映像であると同時に、時代を駆け抜けた塾生、教職員の情熱や息吹を今に伝える、生きた歴史そのものです。現在公開されているシリーズについて、見どころを一挙ご紹介します。
戦後復興の歩み
VIRIBUS UNITIS 力を合せて
ー慶應義塾復興記録 1947~1949ー
タイトルの「VIRIBUS UNITIS」はラテン語で「力をあわせて」という意味です。もとは1909(明治42)年の普通部卒業生が寄贈した石碑に刻まれた言葉。寄贈した塾員たちは、そのわずか40年後に義塾が直面する苦難を想像もしていなかったでしょう。慶應義塾のキャンパスは、太平洋戦争において全国の大学の中でも最大の空襲被害に遭いましたが、先人たちの思いが戦後復興を支えるキーワードのひとつになりました。福澤の時代より伝わる、いかなる時も学問研究の灯を消してはならないという精神をもとに、失われた日常から力強く復興の歩みを進める様子をご覧ください。
本編はこちらから https://t.co/16p0NQBpC8
焼け野原になった医学部、
大学病院の復興
医学部、大学病院がある信濃町キャンパスは、1945年5月24日未明の空襲で施設の6割が焼失しました。災禍にもめげず、戦後まもなく武蔵野分校に移転し開講された基礎医学講座の授業で、加藤元一教授が医学生を指導する姿が残されています。加藤教授は、カエルの神経伝導の研究でノーベル賞候補に挙がったといわれる世界的な研究者です。加藤教授と教え子たちは、実験を支えたカエルたちを供養するために信濃町キャンパスにほど近い笹寺に蝦蟇塚(がまづか)を建立したことでも知られています。

全国に先駆けた男女共学・
慶應義塾中等部の曙
1947年、戦後の新制度の中学として慶應義塾中等部が発足しました。慶應義塾の中学で初となる女子の生徒を迎え入れ、全国的にも男女共学の先駆けとなりました。フィルムでは、男子生徒と女子生徒が同じ教室で活発に意見をかわす様子が見られます。

なぜ?三田キャンパス中庭で行われた
入学式
エンディングは中庭での入学式風景。戦後を象徴するように女子学生の姿も見られますが、なぜ屋外で開催されているのでしょうか。じつはこの映像は大講堂の焼失を意味しています。大講堂は現在の西校舎の位置にあり、ゴシック様式、鉄骨レンガ造りの三田キャンパスにおけるシンボル的建物でした。1922年にアインシュタイン博士が講演を行ったことでも有名なホールですが、1945年の空襲で甚大な被害を受け、義塾は式典を行うホールを失いました。廃墟となった大講堂の屋上から中庭の式典を見下ろすユニコン像は、なお存在感を示しています。

創立90年 慶應義塾記念祭
1947年5月24日、晴天の三田山上で開催された創立90年の記念式典から始まるフィルム。なぜ創立100年ではなく90年なのか。ここにも戦争の影があります。空襲による三田、信濃町キャンパスの焼失と、米軍による日吉キャンパスの接収により、戦後の義塾は惨憺たる状況にありました。本格的な復興にはかなりの時間が見込まれましたが、10年後の創立100年を目標に、義塾復興の機運を醸成するため、盛大な式典を開催する決意をしたのです。義塾の威信をかけた創立90年祭は10日間にわたり開催されました。フィルムにはそのうちの式典と塾生による展覧会、音楽行進が収められており、早慶レガッタと野球の早慶戦で締めくくられています。
本編はこちらから https://youtu.be/fXQYwUgbqnk
焼け跡の式典と錚々たる登壇者の顔ぶれ
復興を強力に推し進めた潮田江次塾長の力強い式辞、塾員代表として登壇した「憲政の神様」尾崎行雄君による祝辞、さらには天皇陛下(昭和天皇)によるおことばといった貴重な映像が残っています。潮田塾長は式辞の中で、慶應義塾は創立以来あくまで民間として独立自尊の精神を実践し、その精神を世に布かんと努力を続けてきたことについて語っています。天皇陛下からは、「幾多の困難があると思うが、福澤諭吉創業の精神を心として、日本再建のため、一層努力することを望む」と、おことばを賜りました。私学として初の天皇陛下の行幸を仰ぎながら、式典を挙げる建物もなく、焼け跡の広場にテント張りの式壇を設けての開催であったことからも時代の苦難が偲ばれます。

快勝した早慶レガッタと、後楽園球場で開催された野球早慶戦
開店当時の松屋浅草店を背景に、吾妻橋から白髭橋まで、颯爽と水上を滑るレガッタの姿。若き血滾る野球の早慶戦は、米軍による神宮球場接収のため、後楽園球場で開催されています。超満員の球場では、柱に上って観戦する姿もみられる熱狂ぶり。義塾野球部はこの年、早稲田大学との王座決定戦で見事勝利をおさめ、天皇杯を授与されました。

高度経済成長、大学紛争後の
躍動
「慶應義塾」(1974年制作)
ナレーション:加山雄三君
“若大将”こと俳優の加山雄三君(法学部政治学科卒)が、親しみやすさをこめて爽やかにナレーションをつとめた広報映画です。塾生たちが集う春の三田キャンパス中庭の和やかな風景から始まり、授業、課外活動、学園祭、入学試験など春夏秋冬の学生生活が描かれます。学生生活風景の中に、卒業生や家族の集いである慶應連合三田会大会、福澤先生誕生記念会や命日墓参、野球の早慶戦の映像が差し挟まれており、義塾にとって大切な伝統行事であることが伝わってきます。
本編はこちらから https://t.co/FkpPKFtdsr
大学紛争も記憶に新しい1970年代前半という時代
フィルムの制作年は1974年。このわずか数年前の1960年代後半は、全国の大学で学園紛争の嵐が吹き荒れ、慶應義塾も一部塾生らが紛争に身を投じていました。一時は事務の本部組織がある塾監局という建物が過激派の学生たちによって占拠される事態になりましたが、義塾は警察組織の導入無しで紛争を終息させた日本で唯一の大学といわれています。フィルム全体を通して映し出される、のびのびと学問や課外活動、伝統行事にのぞむ塾生たちの姿が印象的ですが、大学史上最大の混迷が記憶に新しい時代の風景であることにも想いを馳せてみると、より深い感慨とともにご覧いただけることでしょう。

慶應義塾の国体!?通信教育運動会
慶應義塾大学の通信教育講座は1948年に開講し、同年夏、日本初のスクーリングを実施しました。そんな夏のスクーリングでかつて恒例行事だった運動会。加山君のナレーションでも「慶應義塾の国体とも言えるかもしれません」と言われている通り、全国各地の在住都道府県のプラカードを掲げた、年齢もバックグラウンドも異なる塾生たちの底抜けに明るい表情が印象的です。

じつは上大崎にあった福澤諭吉の墓所
2月3日の福澤先生命日には、福澤が妻の錦さんとともに眠る墓所に多くの義塾関係者が訪れ手を合わせます。現在は港区麻布山善福寺にある墓所ですが、1977年までは品川区上大崎の常光寺にありました。このフィルムには常光寺に墓所があった頃の貴重な墓参の映像が残されています。上大崎の墓所は生前に福澤自らが気に入って選んだ場所でしたが、1977年5月に福澤家の菩提寺である善福寺に移葬されました。常光寺には現在、「福澤諭吉先生永眠之地」という碑が建てられています。

「創立125年記念 慶應義塾」
ナレーション:石坂浩二君
創立125年記念式典は、1983年5月15日に日吉キャンパスにて開催されました。福澤諭吉による建学の精神と慶應義塾命名、大学部の設置、体育会の歴史、創立75年、太平洋戦争からの復興など、慶應義塾125年の歴史と伝統をこのフィルム1本で振り返ることができます。俳優の石坂浩二君(法学部法律学科卒)による心に響くナレーションで、義塾125年の旅路にいざなわれる内容となっています。
本編はこちらから https://t.co/i5ryZbGoSa
1980年代の慶應義塾の国際意識
重要文化財の演説館で講演するケンブリッジ大学ダウニング・コレッジ学長のジョン・バターフィールド博士の肉声が残されています。博士は、義塾とケンブリッジ大学との学術交流に多大の貢献をされたとして、名誉博士の称号を授与されました。創立125年記念式典にも来賓として登壇し、祝辞を述べられています。ケンブリッジ大学ダウニング・コレッジとの交流は、塾生向け夏季講座の開催など、現在も続いています。
また、創立125年関連行事として開催された慶應国際シンポジウム「アジアと日本」で、当時のマレーシア首相マハティール・ビン・モハマド氏が講演しました。満員の会場では塾生、卒業生、教職員が熱心に耳を傾ける様子がみられ、日本全体がまだ西欧志向だった当時、義塾社中はいち早くアジア諸国と交流し、互いに学ぶ重要性を認識していたことがわかります。

大迫力のワグネル・ソサィエティ
特別演奏会
1983年12月4日、上野の東京文化会館大ホールに皇太子殿下ご夫妻(当時)のご臨席を賜り、創立125年記念特別演奏会が開催されました。指揮は山田一雄氏。慶應義塾が誇るワグネル・ソサィエティ男声合唱団、女声合唱団、オーケストラによる大迫力の「第九」の一部を聴くことができます。会場の熱気まで伝わってくる大変貴重な映像です。

慶應義塾公式YouTube「あの日、あの時、映像でよみがえる慶應義塾」シリーズでは、米軍による日吉キャンパスの接収と返還、湘南藤沢キャンパス開設記録など、今後も貴重な映像の公開を予定しています。チャンネル登録の上、乞うご期待ください。
慶應義塾公式YouTube
https://www.youtube.com/user/keiouniversity
サイトマップの始まり
ナビゲーションの始まり