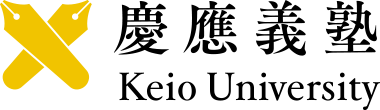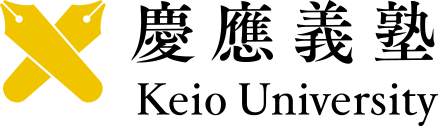ヘッダーの始まり
- ホーム
- Keio Times(特集)一覧
- Keio Times(特集)
本文の始まり
未来の国際医療人を育成
医療系3学部合同 ラオス研修
2018/07/20
「慶應義塾大学医療系3学部合同 ラオス・プライマリヘルスケア保健医療チーム活動プロジェクト」
(プロジェクトリーダー:小池智子 看護医療学部/大学院健康マネジメント研究科准教授)
医学部(1917年開設)、看護医療学部(2001年開設)、薬学部(2008年開設)の医療系3学部が揃って10年、慶應義塾大学では、未来の医療を担う「チーム医療」を見据えたカリキュラムを充実させています。患者中心の医療を提供するために欠かせないのが、多職種の専門家が一丸となって患者にとっての「最良」を考えることです。医師、看護師、薬剤師が1つのチームとなり、医療に取り組むことが求められているのです。チーム医療についての理解を深め、そのより良い在り方を学ぶために始まったのが医療系3学部合同教育です。さまざまなプログラムがある中で、年々その内容に磨きをかけている「ラオス・プライマリヘルスケア保健医療チーム活動プロジェクト」では、医療系学部で学ぶ学生の視点を世界へと広げる貴重な体験型プログラムが用意されています。
「ラオス・プライマリヘルスケア保健医療チーム活動プロジェクト」
ラオスは東南アジアに位置する国です。雨季と乾季があり、熱帯モンスーン気候に属しています。1年中蚊がいるため、蚊によって媒介されるデング熱やマラリアなどに注意が必要です。医療人材や医療設備が不足しているため医療水準は低く、長年にわたり国際協力機構(JICA)が支援活動を進めてきました。「ラオス・プライマリヘルスケア保健医療チーム活動プロジェクト」では、ラオスにおいて支援の土台を築いてきたJICAや世界保健機関(WHO)をはじめとする団体などの支援のもと、それぞれの事務所を訪問します。そこで、開発分野における国際社会共通の目標である「ミレニアム開発目標」や「持続可能な開発目標」の達成状況や取り組み、ヘルスケアの課題などについて生の情報を講義形式で学び、医療機関の見学や母子保健支援プロジェクト活動への参加などを行っています。ラオス保健科学大学の学生との合同交流カンファレンス(英語)も実施するなど、未来を担う国際医療人として知見を深める機会を設けています。
観光では行かない国に
行ってみたい
普通の医療系学生が国際医療に目覚めるプロジェクト
「観光などではなかなか訪れることのない国なので、行ってみたいと思いました。一度は発展途上国をこの目で見たいという思いもありました」と語るのは、医学部5年の古屋光平君。仲の良い友達にこのプログラムを紹介され、応募しました。「ラオス・プライマリヘルスケア保健医療チーム活動プロジェクト」は、ラオス人民民主共和国(以下、ラオス)に10日間滞在し、都市部と村落の両方で医療活動やプライマリヘルスケア活動を体験できるプロジェクト。医学部、看護医療学部、薬学部の学生を対象としています。現地に入る前には、14コマ分の講義と演習により事前学習を行い、日本で知り得るラオスの知識をできる限り叩き込み、現地での活動に備えます。「妊婦が日本の約40倍も亡くなっていることを知り驚きました」(古屋君)
講義と演習を通して、学生たちはそれぞれの専門分野の視点からラオスでの保健医療活動への取り組み方を考えます。

目指すは国際助産師
生の現場での経験から学ぶ
もともと、国際医療活動に興味があり慶應義塾に入学した看護医療学部3年の城戸真和子君は、実際に国際支援の現場を体験できるプロジェクト内容に魅かれて応募したひとりです。
「慶應義塾が国際的な医療研究に力を入れていることは入学前から知っていました。慶應の国際医療関係のプログラムには全て参加する、くらいの気持ちで入学しました」と城戸君。今回のプロジェクトでは特に母子保健分野に関心がありました。臨床実習を行った南部のサラワン県の県病院では、出産に立ち会う機会もありました。
「分娩室はありましたが、ドアがなく、廊下から分娩の様子が丸見えでした。カーテンをつけるなど、患者さんのプライバシーを守ることが必要だと思いました」(城戸君)
看護師的視点から目につくことが多くあったそうです。「現地に行かなければ気がつかなかった発見がいくつもありました」。参加者が、さまざまな視点から必要なことを見つけて、ディスカッションを繰り返す日々を過ごしました。

病院の薬局で掃除担当者が薬を数えるという衝撃的な現場を目にしたのは、薬学部の石橋真理亜君。現地の風習や文化、医療の状況を考えると「これも仕方のないことなのかも」と考えるようになったと話します。
「村ではコミュニティーが生きています。夜になると人々が集まって水たばこを吸っていたのですが、そこが村人にとって情報交換の場にもなっていることに気づきました。私もそこに加わると、言葉はわからなかったのですが、村の一員として認められた気がしました。村ではみんなが協力して生活を営んでいます。村の誰かが病気になれば、家族や近所の人々が皆でそのケアに取り組む姿が見られ、絆の強さを感じました。掃除担当者が薬を数え、患者さんに渡している状況は確かに異様に見えました。人手が足らないという理由でそのようなことが行われていると聞き、正直驚きましたが、“数を数えることなら医療従事者ではない人にもできるから”という現地の病院の方の言葉に、いろいろと気づかされました。人同士のつながりや絆の強いラオスならではの医療の発展を考えるならば、全てを否定する必要はないように感じました」

使われていなかった手洗い場
現地の人が継続できる
保健衛生を考える
滞在10日間のうち、2泊3日は村落に滞在。村の家庭にホームステイをしながら、その地域の学校で保健衛生教育を行います。同プロジェクトでは毎年同じ小学校を訪問しているため、手法や設備など、これまでのプロジェクト参加者から引き継いで、さらに工夫と改善を重ねて取り組んでいます。その一つが、小学校に設置した手洗い場です。プロジェクトに参加したメンバーも、これまでの参加者が2016年に手洗い場を作ったことは聞いていました。ところが、現地に着くと、手洗い場の部品が壊れ、支柱には錆びが浮いていました。野菜を洗うのに利用していたようで、子ども達の手洗いには使われた形跡が見あたりません。この状況を見たメンバーはまず、手洗い場の修繕から始めました。壊れた部品を取り替え、ペンキを塗り、石けんを設置。小学校の先生方とは、手洗い場の管理の方法を話し合い、子ども達には手洗いの大切さを伝え、手洗い場の使い方や手の洗い方の指導を再度行ったのです。


こうした設備の「持ち腐れ」はあらゆるところで見受けられました。
「日本や他の国からの支援で導入された医療機器が、壊れたまま置かれているのを何度か見ました。心音を聞く装置が壊れていたり、歯科で使われる患者さんが口をゆすぐための装置が壊れていたり……。壊れてしまうと現地では修理できる部品や技術がないため、使えなくなるそうです。医療者は、限られた機器で現場を乗り切る必要があります。今回の研修に参加して、『発展途上国』と一括りに考えることはできず、国際医療の現場でも、それぞれの国にそれぞれのニーズと課題があることが見えてきました。ラオスにはラオスの医療発展の仕組み、方法が必要だと感じました」(城戸君)
「医療機器が停電で使えないという話も耳にしました。手洗い場にしてもそうですが、現地で持続してもらえなければ意味がありません。途上国の場合、先進的な技術を導入することも必要ですが、まずは、持続可能な保健医療とは何かを考えることが大切だと痛感しました。今回、僕たちが参加した小学校での保健衛生活動でいえば、“石けん”が課題になると思います。現地の人が石けんを継続的に手に入れるのは難しいので、なにか他の手立てを考えなければと……。宿題をもらって帰りました」(古屋君)



立体的なとらえ方が
チーム医療の強みとなる
2011年に同プロジェクトを立ち上げた看護医療学部の小池智子准教授は、「医療保健チームとして『プライマリヘルスケア活動』に参加して、国際保健における『持続可能な支援』と『チーム・アプローチ』を体験的に学ぶプログラムです。とりわけ、医学、看護学、薬学という異なる分野の視点から、医療の現場で役立つ『統合的に物事をとらえる力』がつきます」と評価します。
「3学部合同で国際保健活動を行うことは、とても意義深いものがあると考えています。国際保健の現場では、日本では経験することのない新たな課題に直面します。そこで問題解決に取り組むには、問題や現象を引き起こしている背景を理解するための、多面的かつ総合的にものを見る力や、文化の違いや多様性を尊重し、持続可能性という観点から現場に相応しい代替案を提案する力、これらを支えるコミュニケーション力が必要です」
「医療は、医学、看護学、薬学それぞれにそれぞれの視点があり、アプローチの仕方があります。これからの医療現場では、個別の専門的な視点だけではなく、多角的にものを見る目が必要となります。例えば、円錐形の物体を、側面からだけ見れば三角形、底面からだけ見たら円形にしか見えませんが、多様な視点を統合することで、立体的にその形をとらえることが可能になります。このプログラムに参加した学生たちは、学年や専門分野を越えて、ディスカッションを重ね、現地で課題に取り組むという体験を通して、多様なチームで学び合い活動することによって生みだされる成果を実感していきます。チーム医療の重要性が叫ばれる昨今の医療現場に欠かせない力を養っていると言えるでしょう」(小池准教授)

また、小池准教授は、国際的な医療活動の経験は、国内での取り組みを考える上でも良い刺激になると参加した学生に伝えています。
「先進国が発展途上国を支援するという一方的な活動ではなく、先進国が途上国から学ぶべき点についてもプロジェクトを通して考えてもらいたいと思っています。例えば、限られた予算や資源で、地域において医療やケアを行うための方策を考える上で、途上国が選択している方法は多くの示唆を提供してくれます。プライマリー医療では高度な機器に頼らないということは日本でも必要なことでしょうし、現代の日本の医療・介護界が抱える人材不足を考えるならば、コミュニティーの中にある力を活用して、専門家でなくてもできるケアやサポートを広げることや、地域の人たちが予防知識の啓蒙を自らの手で行う方法も考えられるわけです。石橋君が経験した、コミュニティーがもっている力を活用して、住民が継続してできることを行うことで成果をあげるという方法は、今の日本の社会が学ばなければならないことの一つですね。これからの日本の医療や介護を変えるイノベーションのヒントを、途上国での活動の経験から得ることができるでしょう」

また、「これまでに参加した学生たちを見ていると、現場で感じる日本との違いによる衝撃は1~2日で冷め、現地の良さに目を開かされ、固有の文化や社会への理解と共感が深まるとともに、これまでの自分の考えや価値感を問い直したり、持続可能な開発のための行動について考える学生が多いと感じます。修了生の中には、この経験がきっかけで、地域医療の現場に進んだ者もいます。また、現地で出会ったJICAやWHOの医療専門家をロールモデルに、将来、国際保健領域での仕事に従事することを目指して、様々な海外研修やプロジェクトにチャレンジしている学生も多く、頼もしく思っています」(小池准教授)
3学部合同で実施する継続的な研修は、日本と世界の医療現場で活躍する未来の医療人の育成にこれからも大きく貢献していくことになるでしょう。


※記事中の所属、学年、職名等は掲載時のものです(動画を除く)。
(参考)慶應義塾大学医療系三学部合同教育
http://ipe.keio.ac.jp/
サイトマップの始まり
ナビゲーションの始まり