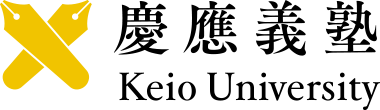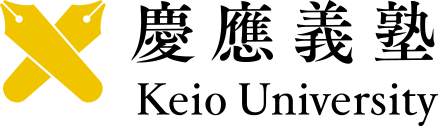ヘッダーの始まり
- ホーム
- 入学案内
- 学部入学案内 - 入試制度
-
各学部における3つの方針
学部入学案内 - 各学部における3つの方針
本文の始まり
- 文学部
-
- 人文社会学科
-
学位授与に関する方針(ディプロマポリシー) <教育目標>
文学部(人文社会学科)は、慶應義塾大学の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を前提として、「文(ことば)」にかかわる広大な領域を対象として、創立者福澤諭吉の「実学の精神」に基づき、実証的に真理を解明し問題を解決してゆく科学的な姿勢と知識および能力を培うことを目標とする。
加えて、総合教育科目、必修語学科目および専門教育科目(各専攻)に関するそれぞれの方針のもとで、所定の要件を満たしたと認められる学生に対して、第2学年進級時に定められる所属専攻に応じて、学士(哲学)、学士(美学)、学士(史学)、学士(文学)、学士(図書館・情報学)、学士(人間関係学)のいずれかの学位を授与する。
<資質・能力目標>
(1)多様な文化や地域につながる幅広い教養を持ち、それを日本語や外国語で適切に説明し、コミュニケーションを行う力。
(2)人文社会科学の学術的な知識と、情報収集能力を身につけたうえで、論理的な思考を行い、効果的なプレゼンテーションを行う力。
(3)社会の中で人文社会科学を学ぶことの意義を自覚し、自ら設定した目標の達成や社会問題の解決を、ふさわしい方法で行う力。
(4)学修の最終成果である卒業論文を執筆し、専門的な領域において、先人の成果をふまえた新たな展望を提示する力。あるいは、卒業試験において、同等の内容を提示する力。
教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラムポリシー) <教育課程の編成>
文学部(人文社会学科)は、「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」に掲げる資質・能力目標を養成するために、総合教育科目、必修語学科目および専門教育科目から構成される教育課程(カリキュラム)を体系的に編成する。
<教育課程の実施>
この教育課程の編成のもと、以下の教育方法を組み合わせて教育を実施する。
- (1)基礎的かつ包括的な知識と問題意識の獲得を目指し、人文社会科学に加え、自然科学や学際的な分野も包含する多様な科目群を設置する。
- (2)自ら課題を見出し、その解決を目指す能力を身につけるため、講義科目、演習科目、実験科目、フィールドワークなどにおいて、学生が主体となる能動的な授業を拡充する。
- (3)知的探究への動機づけと実践力を育成するため、専門的な知識や技能を習得する科目群と学際的な科目群を共に履修する機会を設ける。
<学修成果の評価方法>
本学部の教育課程により修得すべき資質・能力目標に対する学修成果の評価は、全塾としてのアセスメントプランの考え方のもと、各科目において定める成績評価基準等に基づいた直接的な指標により行われるほか、各種アンケートや調査等を含めた定量的・定性的、直接的・間接的な指標を用いて評価される。具体的には、①学生による授業評価、②入学経路別成績分布調査、③休学や退学の状況、④プレイスメントテストなどを用いる。
<資質・能力目標と教育内容との関係>
(1)多様な文化や地域につながる幅広い教養を持ち、それを日本語や外国語で適切に説明し、コミュニケーションを行う力。
→総合教育科目、必修語学科目において、学士課程での学びの軸となる幅広い見識、学習のための基礎的技能、着実な言語運用能力を身につけ、専門教育科目においてさらなる応用力を養う。
(2)人文社会科学の学術的な知識と、情報収集能力を身につけたうえで、論理的な思考を行い、効果的なプレゼンテーションを行う力。
→総合教育科目、必修語学科目での学習成果をふまえ、専門教育科目において、所属する各専攻にかかわる基礎的な知識を修得し、次第に高度な専門的学識や技能の習得を目指す。
(3)社会の中で人文社会科学を学ぶことの意義を自覚し、自ら設定した目標の達成や社会問題の解決を、ふさわしい方法で行う力。
→演習や、専攻によっては実験、フィールドワークにかかわる科目を組み合わせて履修することにより、研究・学習課題を自ら定め、達成する能力を育成する。また、専攻外の専門教育科目等の履修も可能とし、広く人文社会科学領域に関する理解を深める機会を設ける。
(4)学修の最終成果である卒業論文を執筆し、専門的な領域において、先人の成果をふまえた新たな展望を提示する力。あるいは、卒業試験において、同等の内容を提示する力。
→主として専門教育科目の研究会において、各自の研究テーマを探求し、ディスカッションやフィードバックを通じて自己の研究過程を客観的に評価し、より高次な問題解決に挑む力を養う。卒業試験コースのある専攻においては、それぞれ定める科目において同等の能力を育成する。
入学者の受入れに関する方針(アドミッションポリシー) <求める学生像>
- (1)慶應義塾の精神に対する十分な理解、および学問に対する意欲と向上心を持つ。
- (2)先人による古典類から最新の研究成果が書かれた論文に至るまでの諸文献を読み込み、理解するための基礎となる語学力(日本語、および英語・フランス語・ドイツ語)を身につけている。
- (3)与えられた課題に対して論理的に思考し、それに対する自分の考えを正確かつ十分に記述する能力を有する。
- (4)現在の社会や文化の成り立ちを理解するための基礎となる歴史的な知識(日本史または世界史)を持つ。
- (5)文学部が設置している専攻(哲学、倫理学、美学美術史学、日本史学、東洋史学、西洋史学、民族学考古学、国文学、中国文学、英米文学、独文学、仏文学、図書館・情報学、社会学、心理学、教育学、人間科学)が対象とするいずれかの学問に対する関心・好奇心を有する。
<選抜の基本方針>
このような入学者を幅広く受け入れるため、(1)一般選抜、(2)自主応募制による推薦入学者選考、(3)外国人留学生対象入学試験により選抜を実施する。
- (1)一般選抜
外国語・地理歴史・小論文の三科目の試験による選抜であり、文学部にふさわしい高い学力を要求する。 - (2)自主応募制による推薦入学者選考
高等学校で一定の評点に達していることを条件に、在学中の活動実践や社会的活動をも加味した総合的な考査によって選抜する。 - (3)外国人留学生対象入学試験
学業成績と勉学意欲を勘案した選抜を行う。
- 人文社会学科・哲学専攻・学士(哲学)
-
学位授与に関する方針(ディプロマポリシー) <教育目標>
慶應義塾大学の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を前提として、西洋哲学に対する理解を深めながら批判的思考力を養い、論理的表現力を磨くとともに、現代社会の諸問題に対して普遍的かつ自律的な視点から考察できる人材の育成を目標とする。加えて、教育課程において定める所定の要件を満たした学生に対し、学士(哲学)の学位を授与する。
<資質・能力目標>
資質・能力目標(1):古今の西洋哲学の文献を正確に理解できること。またそのために必要な語学力と批判的思考力を身につけていること。
資質・能力目標(2):口頭発表・ディスカッション・文章表現などにおいて説得力ある議論・論証ができるだけの論理的表現力を身につけていること。
資質・能力目標(3):人間とそれを取り巻く世界、人間が形成してきた知識(諸科学)、信念体系、価値体系について、原理的かつ総合的な反省的考察をおこなうことができること。
資質・能力目標(4):変転めまぐるしい現代社会の只中にあっても、問題に対してつねに原理的かつ批判的な考察を加えようとする合理的で自律的な思考主体・表現主体であると同時に、いかなる問題に直面しても、時流に流されることなく、つねに普遍的な観点に立とうとする行為主体であること。
資質・能力目標(5):学修の最終成果である卒業論文を執筆し、専門的な領域において、先人の成果をふまえた新たな展望を提示する力。
<卒業論文における審査項目>
卒業論文は次の審査項目を満たすものとする。
1.テーマ・問題意識が明確である。
2.先行研究を踏まえている。
3.方法が目的に適っている。
4.内容が論理的で一貫している。
5.形式が学術論文として適切である。
教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラムポリシー) <教育課程の編成>
文学部人文社会学科哲学専攻(学士:哲学)は、「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」に掲げる資質・能力目標を養成するために、総合教育科目、必修語学科目および専門教育科目から構成される教育課程(カリキュラム)を体系的に編成する。
<教育課程の実施>
この教育課程の編成のもと、以下の教育方法を組み合わせて教育を実施する。
- (1)基礎的かつ包括的な知識と問題意識の獲得を目指し、人文社会科学に加え、自然科学や学際的な分野も包含する多様な科目群を設置する。
- (2)自ら課題を見出し、その解決を目指す能力を身につけるため、講義科目、演習科目などにおいて、学生が主体となる能動的な授業を拡充する。
- (3)知的探究への動機づけと実践力を育成するため、専門的な知識や技能を習得する科目群と学際的な科目群を共に履修する機会を設ける。
<学修成果の評価方法>
本専攻の教育課程により修得すべき資質・能力目標に対する学修成果の評価は、全塾としてのアセスメントプランの考え方のもと、各科目において定める成績評価基準等に基づいた直接的な指標により行われるほか、各種アンケートや調査等を含めた定量的・定性的、直接的・間接的な指標を用いて評価される。具体的には、①学生による授業評価、②入学経路別成績分布調査、③休学や退学の状況、④プレイスメントテストなどを用いる。
<資質・能力目標と教育内容との関係>
資質・能力目標(1):古今の西洋哲学の文献を正確に理解できること。またそのために必要な語学力と批判的思考力を身につけていること。
→総合教育科目、必修語学科目において、学士課程での学びの軸となる幅広い見識、学習のための基礎的技能、着実な言語運用能力を身につけ、専門教育科目においてさらなる応用力を養う。
資質・能力目標(2):口頭発表・ディスカッション・文章表現などにおいて説得力ある議論・論証ができるだけの論理的表現力を身につけていること。
→総合教育科目、必修語学科目での学修成果をふまえ、専門教育科目において、哲学にかかわる基礎的な知識を修得し、次第に高度な専門的学識や技能の習得を目指す。
資質・能力目標(3):人間とそれを取り巻く世界、人間が形成してきた知識(諸科学)、信念体系、価値体系について、原理的かつ総合的な反省的考察をおこなうことができること。
→演習にかかわる科目を組み合わせて履修することにより、研究・学習課題を自ら定め、達成する能力を育成する。また、専攻外の専門教育科目等の履修も可能とし、広く人文社会科学領域に関する理解を深める機会を設ける。
資質・能力目標(4):変転めまぐるしい現代社会の只中にあっても、問題に対してつねに原理的かつ批判的な考察を加えようとする合理的で自律的な思考主体・表現主体であると同時に、いかなる問題に直面しても、時流に流されることなく、つねに普遍的な観点に立とうとする行為主体であること。
→主として専門教育科目の研究会および卒業試験において、各自の研究テーマを探求し、ディスカッションやフィードバックを通じて自己の研究過程を客観的に評価し、より高次な問題解決に挑む力を養う。
資質・能力目標(5):学修の最終成果である卒業論文を執筆し、専門的な領域において、先人の成果をふまえた新たな展望を提示する力。
→卒業論文を執筆するために、「哲学研究会」を必修科目として設置する。学生は自らの関心に従って研究テーマを選択し、所属する研究会の担当教員による指導を受けることができる。
入学者の受入れに関する方針(アドミッションポリシー) <求める学生像>
- (1)慶應義塾の精神に対する十分な理解、および学問に対する意欲と向上心を持つ。
- (2)先人による古典類から最新の研究成果が書かれた論文に至るまでの諸文献を読み込み、理解するための基礎となる語学力(日本語、および英語・フランス語・ドイツ語)を身につけている。
- (3)与えられた課題に対して論理的に思考し、それに対する自分の考えを正確かつ十分に記述する能力を有する。
- (4)現在の社会や文化の成り立ちを理解するための基礎となる歴史的な知識(日本史または世界史)を持つ。
- (5)文学部が設置している専攻(哲学、倫理学、美学美術史学、日本史学、東洋史学、西洋史学、民族学考古学、国文学、中国文学、英米文学、独文学、仏文学、図書館・情報学、社会学、心理学、教育学、人間科学)が対象とするいずれかの学問に対する関心・好奇心を有する。
<選抜の基本方針>
このような入学者を幅広く受け入れるため、(1)一般選抜、(2)自主応募制による推薦入学者選考、(3)外国人留学生対象入学試験により選抜を実施する。
- (1)一般選抜
外国語・地理歴史・小論文の三科目の試験による選抜であり、文学部にふさわしい高い学力を要求する。 - (2)自主応募制による推薦入学者選考
高等学校で一定の評点に達していることを条件に、在学中の活動実践や社会的活動をも加味した総合的な考査によって選抜する。 - (3)外国人留学生対象入学試験
学業成績と勉学意欲を勘案した選抜を行う。
- 人文社会学科・倫理学専攻・学士(哲学)
-
学位授与に関する方針(ディプロマポリシー) <教育目標>
倫理学専攻は、慶應義塾大学の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を前提として、古今東西の思想家たちとの対話を通じて人間の生き方を探究し、思想家の精神的創作活動の場としての文化の本質を問い、そして、近現代の自然観や生命観、人間観や社会観を問い直す能力を培うことを目標とする。加えて、教育課程において定める所定の要件を満たした学生に対し、学士(哲学)の学位を授与する。
<資質・能力目標>
資質・能力目標(1):人間の生き方を探究する視点と方法を確立するために必要とされる、倫理学の主要理論と理論史に関する基本的な知識を習得している。
資質・能力目標(2):倫理学の主要文献を原語で正確に読解するために必要なレベルの外国語(原則として ドイツ語・フランス語・英語)を習得している。
資質・能力目標(3):多様な倫理思想・宗教思想についての理解を深め、人間の根底に迫るとともに、多文化社会における人間の生のあり方を反省する力。
資質・能力目標(4):科学技術の発展や環境破壊、戦争、グローバル化など、現代社会の身近な問題を手がかりにして、近現代の自然観や生命観、人間観や社会観を問い直す力。
資質・能力目標(5):倫理学上重要な理論とそれに関する先端的研究について、一定の知識を有している。
資質・能力目標(6):卒業論文において、人間の生き方や社会のあり方について考察すべき問いを自らの関心に従って選択し、先行研究をふまえながら、それに対する解答を首尾一貫して提示する力。
<卒業論文における審査項目>
学修の最終成果である卒業論文は、次の審査項目を満たすものとする。
1.テーマ・問題意識が明確である
2.先行研究を踏まえている
3.方法が目的に適っている
4.内容が論理的で一貫している
5.形式が学術論文として適切である
教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラムポリシー) <教育課程の編成>
文学部人文社会学科倫理学専攻(学士:哲学)は「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」に掲げる資質・能力目標を養成するために、総合教育科目、必修語学科目および専門教育科目から構成される教育課程(カリキュラム)を体系的に編成する。
<教育課程の実施>
この教育課程の編成のもと、以下の教育方法を組み合わせて教育を実施する。
- (1)基礎的かつ包括的な知識と問題意識の獲得を目指し、多様な科目群を設置する。
- (2)自ら課題を見出し、その解決を目指す能力を身につけるため、講義科目、演習科目などにおいて、学生が主体となる能動的な授業を拡充する。
- (3)知的探究への動機づけと実践力を育成するため、専門的な知識や技能を習得する科目群と学際的な科目群を共に履修する機会を設ける。
<学修成果の評価方法>
本専攻の教育課程により修得すべき資質・能力目標に対する学修成果の評価は、全塾としてのアセスメントプランの考え方のもと、各科目において定める成績評価基準等に基づいた直接的な指標により行われるほか、各種アンケートや調査等を含めた定量的・定性的、直接的・間接的な指標を用いて評価される。具体的には、①学生による授業評価、②入学経路別成績分布調査、③休学や退学の状況、④プレイスメントテストなどを用いる。
<資質・能力目標と教育内容との関係>
資質・能力目標(1):人間の生き方を探究する視点と方法を確立するために必要とされる、倫理学の主要理論と理論史に関する基本的な知識を習得している。
→倫理学の主要理論と理論史に関する基本的な知識を習得するための科目として、「倫理学概論」「西洋哲学倫理学史」(第2学年履修指定科目)を必修科目として設置する。
資質・能力目標(2):倫理学の主要文献を原語で正確に読解するために必要なレベルの外国語(原則として ドイツ語・フランス語・英語)を習得している。
→倫理学の主要文献を原語で読解するための科目として、「哲学倫理学原典講読(独・仏)」(第 2学年進級条件科目)を必修科目として設置する。より発展的な学習のため、「倫理学洋書講読」を設置する。
資質・能力目標(3):多様な倫理思想・宗教思想についての理解を深め、人間の根底に迫るとともに、多文化社会における人間の生のあり方を反省する力。
→多様な倫理思想・宗教思想の理解を深めるための科目として、「日本倫理思想」、「東洋倫理思想」、「キリスト教概論」、「仏教学概論」(全専攻共通科目)を設置する。
資質・能力目標(4):科学技術の発展や環境破壊、戦争、グローバル化など、現代社会の身近な問題を手がかりにして、近現代の自然観や生命観、人間観や社会観を問い直す力。
→現代社会の身近な問題を手がかりにして近現代の自然観や生命観、人間観や社会観を 問い直すための科目として、「倫理学の課題」を必修科目として設置する。
資質・能力目標(5):倫理学上重要な理論とそれに関する先端的研究について、一定の知識を有している。
→倫理学上重要な諸理論を詳細にわたって理解し、その先端的研究に触れるための科目として、「哲学倫理学特殊」を設置する。
資質・能力目標(6):卒業論文において、人間の生き方や社会のあり方について考察すべき問いを自らの関心に従って選択し、先行研究をふまえながら、それに対する解答を首尾一貫して提示する力。
→卒業論文を執筆するために、「倫理学研究会」(第3学年進級条件科目、 第4学年卒業要件科目)を必修科目として設置する。学生は自らの関心に従って研究テーマを選択し、所属する研究会の担当教員による指導を受けることができる。
入学者の受入れに関する方針(アドミッションポリシー) <求める学生像>
- (1)慶應義塾の精神に対する十分な理解、および学問に対する意欲と向上心を持つ。
- (2)先人による古典類から最新の研究成果が書かれた論文に至るまでの諸文献を読み込み、理解するための基礎となる語学力(日本語、および英語・フランス語・ドイツ語)を身につけている。
- (3)与えられた課題に対して論理的に思考し、それに対する自分の考えを正確かつ十分に記述する能力を有する。
- (4)現在の社会や文化の成り立ちを理解するための基礎となる歴史的な知識(日本史または世界史)を持つ。
- (5)文学部が設置している専攻(哲学、倫理学、美学美術史学、日本史学、東洋史学、西洋史学、民族学考古学、国文学、中国文学、英米文学、独文学、仏文学、図書館・情報学、社会学、心理学、教育学、人間科学)が対象とするいずれかの学問に対する関心・好奇心を有する。
<選抜の基本方針>
このような入学者を幅広く受け入れるため、(1)一般選抜、(2)自主応募制による推薦入学者選考、(3)外国人留学生対象入学試験により選抜を実施する。
- (1)一般選抜
外国語・地理歴史・小論文の三科目の試験による選抜であり、文学部にふさわしい高い学力を要求する。 - (2)自主応募制による推薦入学者選考
高等学校で一定の評点に達していることを条件に、在学中の活動実践や社会的活動をも加味した総合的な考査によって選抜する。 - (3)外国人留学生対象入学試験
学業成績と勉学意欲を勘案した選抜を行う。
- 人文社会学科・美学美術史学専攻・学士(美学)
-
学位授与に関する方針(ディプロマポリシー) <教育目標>
慶應義塾大学の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)を前提として、古今東西の美と芸術に関する様々な知識と研究方法を修得しながら、優れたコミュニケーション能力を有し、人間を尊重し、自らと他者を理解することによって多様な価値を認める深い人間性を養う。また、さまざまな分野でリーダーシップを発揮し、社会の各方面に貢献できる人材となることを目標とする。加えて、教育課程において定める所定の要件を満たした学生に対し、学士(美学)の学位を授与する。
<資質・能力目標>
資質・能力目標(1):美学、芸術学、美術史学、音楽学、アート・マネジメント等、美と芸術に関する各分野の学問に関して、本質的で幅広い知識と教養を身につける。
資質・能力目標(2):芸術の諸分野についての基礎的教養を身につけ、あわせてイメージやパフォーマンス等の非言語的対象を把握し、それを適切に言語化する基本的リテラシーを身につける。
資質・能力目標(3):美学や各芸術分野についての文献講読を通して、基本的な外国語・日本語(古典)の読解力を身につける。
資質・能力目標(4):研究テーマに応じて適切な情報の収集と分析を行い、科学的・論理的に思考し、批判的に考えることができる力。
資質・能力目標(5):各研究会での研究・発表等の活動に積極的に参加し、適確な文章をもって、学問的な評価に耐えうる卒業論文を執筆する力。
<卒業論文における審査項目>
学修の最終成果である卒業論文は次の審査項目を満たすものとする。
1.テーマ・問題意識が明確である。
2.先行研究を踏まえている。
3.方法が目的に適っている。
4.内容が論理的で一貫している。
5.形式が学術論文として適切である。
教育課程の編成及び実施に関する方針(カリキュラムポリシー) <教育課程の編成>
文学部人文社会学科美学美術史学専攻(学士:美学)は、「卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)」に掲げる資質・能力を養成するために、専門教育科目から構成される教育課程(カリキュラム)を体系的に編成する。
<教育課程の実施>
この教育課程の編成のもと、以下の教育法を組み合わせて教育を実施する。
- (1)美学・芸術学、美術史学と音楽学、アート・マネジメントなどの芸術諸分野にわたる多様な科目群を設置することで、美と芸術に関する基礎的かつ包括的な知識と問題意識の獲得を目指す。
- (2)自ら課題を見出し、その解決を目指す能力を身につけるため、講義科目、演習科目、フィールドワーク(美術館、博物館等における見学・調査)などにおいて、学生が主体となる能動的な授業を拡充する。
- (3)知的探求と実践力の育成のために、専攻の必修科目とともに、大学設置の専門教育科目を選択科目として履修する機会を設ける。
<学修成果の評価方法>
本専攻の教育課程により修得すべき資質・能力目標に対する学修成果の評価は、全塾としてのアセスメントプランの考え方のもと、各科目において定める成績評価基準等に基づいた直接的な指標により行われるほか、各種アンケートや調査等を含めた定量的・定性的、直接的・間接的な指標を用いて評価される。具体的には、①学生による授業評価、②入学経路別成績分布調査、③休学や退学の状況、④プレイスメントテストなどを用いる。
<資質・能力目標と教育内容との関係>
資質・能力目標(1):美学、芸術学、美術史学、音楽学、アート・マネジメント等、美と芸術に関する各分野の学問に関して、本質的で幅広い知識と教養を身につける。
→美学や芸術学、芸術の諸分野、そしてアート・マネジメントに関する概説と各論等、多様な授業を設置する。
資質・能力目標(2):芸術の諸分野についての基礎的教養を身につけ、あわせてイメージやパフォーマンス等の非言語的対象を把握し、それを適切に言語化する基本的リテラシーを身につける。
→芸術の諸分野に関する概論、概説、各論等に加え、主に第2学年を対象とした「芸術研究基礎」や「美学美術史学演習」において、基礎的な専門用語や概念を理解し、作品記述の方法を身につけることで、非言語的対象を言語化するための基本的リテラシーを養う。
資質・能力目標(3):美学や各芸術分野についての文献講読を通して、基本的な外国語・日本語(古典)の読解力を身につける。
→芸術の諸分野についての十分な学問的アプローチを可能にするため、外国語(英語・第2外国語)・日本語(古典)のリテラシーを身につけることを目的に、「原典講読」を必修科目として履修する。
資質・能力目標(4):研究テーマに応じて適切な情報の収集と分析を行い、科学的・論理的に思考し、批判的に考えることができる力。
→「芸術研究基礎」や「美学美術史学演習」において、基本文献や研究方法、資料の扱い方などを学び、「美学美術史学研究会」におけるディスカッションや研究発表の実践を通じて、情報収集の方法と分析、科学的な思考能力を養う。
資質・能力目標(5):各研究会での研究・発表等の活動に積極的に参加し、適確な文章をもって、学問的な評価に耐えうる卒業論文を執筆する力。
→第3、第4学年の学生は、必ず「美学美術史学研究会」を履修し、同研究会の担当教員の下で研究・発表を行い、第4学年の学生は卒業論文を執筆する。
入学者の受入れに関する方針(アドミッションポリシー) <求める学生像>
- (1)慶應義塾の精神に対する十分な理解、および学問に対する意欲と向上心を持つ。
- (2)先人による古典類から最新の研究成果が書かれた論文に至るまでの諸文献を読み込み、理解するための基礎となる語学力(日本語、および英語・フランス語・ドイツ語)を身につけている。
- (3)与えられた課題に対して論理的に思考し、それに対する自分の考えを正確かつ十分に記述する能力を有する。
- (4)現在の社会や文化の成り立ちを理解するための基礎となる歴史的な知識(日本史または世界史)を持つ。
- (5)文学部が設置している専攻(哲学、倫理学、美学美術史学、日本史学、東洋史学、西洋史学、民族学考古学、国文学、中国文学、英米文学、独文学、仏文学、図書館・情報学、社会学、心理学、教育学、人間科学)が対象とするいずれかの学問に対する関心・好奇心を有する。
<選抜の基本方針>
このような入学者を幅広く受け入れるため、(1)一般選抜、(2)自主応募制による推薦入学者選考、(3)外国人留学生対象入学試験により選抜を実施する。
- (1)一般選抜
外国語・地理歴史・小論文の三科目の試験による選抜であり、文学部にふさわしい高い学力を要求する。 - (2)自主応募制による推薦入学者選考
高等学校で一定の評点に達していることを条件に、在学中の活動実践や社会的活動をも加味した総合的な考査によって選抜する。 - (3)外国人留学生対象入学試験
学業成績と勉学意欲を勘案した選抜を行う。
- 人文社会学科・日本史学専攻・学士(史学)
-