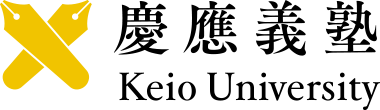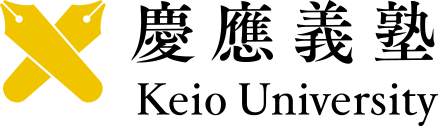ヘッダーの始まり
本文の始まり
2024年度大学学部卒業式 式辞
2025年3月24日
慶應義塾長 伊藤 公平
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。ご家族の皆様にも心からお慶びを申し上げます。本日、ここ日吉記念館において全学部が一斉に集う卒業式が挙行できるという幸せを、私たち慶應義塾教職員も噛み締めています。と申しますのは、今日卒業される皆さんの多くが2021年4月というコロナ禍に入学されました。皆さんにとって、コロナ禍での大学選びや受験はさぞや不安で困難であったことでしょう。それだけに今日という日を迎えられた皆さんの努力、そして、ご家族のご支援に心からの称賛を送ります。
さて、皆さんの卒業にあたり、再度、「慶應義塾の目的」を確認したいと思います。
「慶應義塾は単に一所の学塾として自から甘んずるを得ず。其目的は我日本国中に於ける気品の泉源、智徳の模範たらんことを期し、之を実際にしては居家、処世、立国の本旨を明にして、之を口に言ふのみにあらず、躬行実践、以て全社会の先導者たらんことを欲するものなり」
そう、皆さんは「全社会の先導者」を目指して勉学に励み、課外活動に精を出し、生涯の友と出会ってきました。慶應義塾の「義塾」とは英国のpublic schoolの意味が込められ、まさに公共の発展に尽くすという高い志をもった学生が集まる塾ということです。高い志を持ち続けること、理想を追求し続けることは、簡単ではありません。しかし人間だれにでも存在価値があります。だからこそ皆さん一人ひとりの志や尊厳は、人間社会において何よりも尊いものなのです。これが独立自尊の精神です。一人ひとりの存在意義を基点とするということは、民主主義の理想を追求するということです。先導者と聞くと、何か特別な立場の強いリーダーを思い浮かべる方がいるかもしれませんが、それは慶應義塾の考えとは違います。家族、仕事、社会といった大きさの異なる集団が、チームワークよく物事を正しい方向に進める、そのようなグループこそが先導者集団なのです。今日卒業される皆さんは、これからどのような職、どのような役割を得ていくとしても、独立自尊の先導者としてより良い社会を作っていく役目を、それぞれの立場で果たしていってください。
さて、独立自尊の基盤が「自由」です。福澤先生は、著書『学問のすゝめ』の初編の中に、4,700字ほどの長さですから原稿用紙にしてわずか12枚程度の文章の中に、「自由」という単語を14回登場させました。「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らずと云えり」から始まり、実際にそうであれば誰もが「自由自在、互いに人の妨げをなさずしておのおの安楽にこの世を渡らしめ給う」はずだと述べています。しかし現実はそうではない。その違いはどこから生じるかというと、それはただ単に学ぶか学ばないかの差だと福澤先生は断言します。人は学び続けなければならないということです。今日卒業する皆さんは慶應義塾大学での生活を通じて、生涯を通じて学び続ける力をつけました。大学で一生懸命学んだことも大事ですが、それ以上に大切なのが生涯にわたり学び続けるということであり、そのために必要とされる実力や志や友人を慶應義塾大学で習得したのです。ハーバードビジネスレビュー誌に最近発表された論文によると、現代のテクノロジースキルの平均寿命は5年で、短いものではたったの2年半だそうです。つまり、自分が身につけたスキルは2年半から5年で陳腐化するということです。よってこれから次々と皆さんに降ってくる仕事上の新しい挑戦を克服するためにも、学び続ける力が必要なことは明らかです。しかし、本当の意味で、何のために学び続けるか?と言えば、それは個人としての自由独立を得るためです。そして個人の自由独立を、福澤先生がおっしゃった「一身独立して、一国独立する」の言葉のとおり、国や社会としての自由独立につなげるためであります。
具体的な例を挙げてみましょう。皆さんの多くがSNSを通じてさまざまな情報を得ていると思います。しかし、皆さんがSNSを通して得る情報は、偏っていたり、間違っていたり、ある側面のみを切り取っていることが多々あります。そして、そのような情報をもとに皆さんが思考を巡らし判断を下すとすれば、皆さんは自由を謳歌していると言えるでしょうか?先々週、慶應義塾では、『サピエンス全史』で有名なユヴァル・ノア・ハラリさんをお迎えして講演会を実施しました。そのハラリさんの近著『Nexus-情報の人類史』には次の問題提起がされています。SNS等を通じた皆さんの行動はSNSを運営するプラットフォームに筒抜けです。その情報をAI解析されることで、皆さんそれぞれの趣味や政治的スタンスや宗教などに合わせた情報や広告が、文字通り「選び抜かれ」て皆さんに提供されてきます。テーラーメード、すなわち偏った情報のみがフィードされてきます。その中には人々の考え方を操ろうとするプロパガンダも当然のように含まれます。よって、自分自身の意思ですべてを自由に決めていると思ったとしても、SNSから提供される情報に頼っているケースでは、皆さんの考え方や行動が外部の力によって操作されているのです。福澤先生は『学問のすゝめ』の中で、自由に伴う責任を次のように述べています。「ただ自由自在とのみ唱えて分限を知らざれば我儘(わがまま)放蕩に陥ること多し。」そして「自由と我儘との界(さかい)は、他人の妨げをなすとなさざるとの間にあり。」すなわち、自由というものは他人に悪影響を及ぼさない範囲であると定義しています。SNSで流されるプロパガンダや偽情報は人間が作ったものであり、私たちの自由を侵しています。また、正しい情報だとしても、ある側面だけを切り取った情報のみをSNSが届けるとすれば、それは相手の自由を制限するという意味で悪質です。だからこそ皆さんには、広くさまざまな側面を捉えた事実に基づく情報を、汗をかいて自分で入手して、それらの情報を多角的に捉える学びを続けて、周りの仲間との議論を深めて、社会を正しく導く活動に勤しんでもらいたいのです。そのための一つの方法は、SNSなどで無料で(タダで)情報を入手することは控えめにして、有料の新聞記事や書籍を集めて読むことです。タダほど怖いものはないと言いますが、SNS等で情報が無料で得られるということ自体に、何か裏があることを疑わなければなりません。
さて、自らの自由独立を護ると同様に必要なのが、他人の自由独立を護ることです。これこそが独立自尊の精神です。『学問のすゝめ』では、国の役割として、「政府は法令を設けて悪人を制し、善人を保護す。」と記されています。善人を保護するということは、悪人から守るということと共に、国民の自由を保障し、そして本当に困っている人を助ける(保護する)という意味が込められています。ところが今、世界中の民主主義国家において、国民の政治に対する利己的な要求が増えています。そして、ポピュリスト的な政治家が登場して、どんな不満も解消できると豪語して選挙に勝つと、自分の支持者のみを優先して、自分に異議を唱える国民の自由を奪うという状況が散見されます。日本はまだその点においては耐えていますが、それでも、社会的弱者や若者やエッセンシャルワークを支えてくださっている外国人の声が政治に届きにくい状況ですので、その人たちの自由自在を支援していく努力が、私たちには求められています。福澤先生は著書『西洋事情』の中で19世紀半ばの欧米の様子を紹介し、特に病院や養護施設や学校や博物館などが有志の寄付で支えられていることを紹介しています。そして先生は、不条理によって厳しい境遇におかれた人々を、物心両面において助けるという手本を示しました。北里柴三郎博士はドイツ留学中に、東大時代の恩師の論文を否定する実験結果を発表したことで、ドイツから帰国後の日本での行き場所を失いました。この不条理に対して、福澤先生が自分の土地や私財を提供し、さらには民間からの寄付も募って北里博士のために伝染病研究所をスタートしたことは有名な話です。これ以外にも福澤先生と慶應義塾の先輩方は、不条理に見舞われた多くの人や社会的弱者を、民の力で支援してきました。よって皆さんが卒業して収入を得る立場になりましたら、直ちに、非営利団体(NPO)や公益法人などの支援を、最初は本当にわずかの額で結構ですから、恵まれた人の義務として始めてください。「今年はいくらを寄付しよう」とまずは総額を決めて、それを国の支援が届きにくい貧困、孤児、難民、被災者といった社会的弱者らを支援するNPO、芸術や言論の自由を支援するといった文化・社会活動に関するNPO、さまざまな学校法人などに分配していくのです。そのプロセスを通して、皆さんはいろいろな社会課題の存在を学び、それらの解決に取り組む素晴らしい団体や人々の存在を知ることができます。「国を支えて、国を頼らず」というのも福澤先生の言葉ですが、まさに義塾の一員としての、このような活動自体が大きな学びであり、社会貢献です。
本日は25年前に卒業された2000年三田会の先輩たちがここ日吉記念館に集まり、皆さんの門出を祝ってくださっています。この先輩方は慶應義塾社中の目的を体現されてきた方々です。25年後には、皆さんがこの卒業式に招かれます。その時には25年間の自分達の努力と連帯によって、日本を、世界をより良いものにしてきたことに胸を張ってください。そして、25年後の卒業生たちの旅立ちを一緒に祝ってください。そのことを私からお願いして式辞といたします。ご卒業おめでとうございます。
サイトマップの始まり