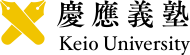メインカラムの始まり
[ステンドグラス] 体育事始め
1995/07/01 (「塾」1995年No.3(No.192)掲載)
現在、38部を擁する慶應義塾体育会。
この体育会が創立されたのは明治25年5月のことだが、その前史をさかのぼると芝新銭座時代にたどり着く。
日本で最初に体育の重要性を唱え、それを教育に導入したのは、福澤諭吉なのである。
この体育会が創立されたのは明治25年5月のことだが、その前史をさかのぼると芝新銭座時代にたどり着く。
日本で最初に体育の重要性を唱え、それを教育に導入したのは、福澤諭吉なのである。
「まず獣身を成してのち人心を養う」——独立独行の生活に欠かせない心身の健康を養う目的で教育にスポーツを取り入れるという、西洋流の体育思想に基づいた福澤諭吉の主張は、義塾創立以来の基本方針でもある。芝新銭座時代にはすでに体育教育が実践され、明治4年に義塾が三田へ移転すると、馬術、剣道、柔道、器械体操などが盛んになった。明治17年には野球が導入され、22年には「三田べ-スボール倶楽部」が結成された。
こうした状況の中、明治25年5月、柔道・剣道・野球・端艇・弓術・操練・徒歩の7部を組織的に統一する「慶應義塾体育会」が創立された。このときの評議員全記録には、体育会について「是迄の春秋運動会費を此倶楽部に給与して、春秋弐回の運動会を催さしむる事」とあり、当時の塾内におけるその役割を知ることができる。当時、「運動会」という言葉は今日より広義に使われており、遠足会なども運動会と呼ばれていた。義塾で初めて"運動会〟が開かれたのは明治16~17年という記録もあるが、今日いう意味での運動会は明治19年6月6日、三田山上の運動場で開催されたものが最初だったようである。その後、「慶應の運動会」は東京の市民の間で評判となり、明治28年には一万人の見物人を数えるほどとなった。
体育会では、その後も新たなスポーツが導入され、テニス、水泳、ラグビーなどの各部が創部された。明治36年には早慶野球戦が開始され、39年、両校学生の応援が過熱するあまり試合が中止されるまでになった。大正期に入ると体育会はますます発展し、14部を擁するに至った。このころ、各部の技術は著しく向上し、対外的に華々しい活躍を繰り広げていた。中でも、昭和期にかけて数度にわたりオリンピック大会へ塾生・塾員選手を送リ出したことは、特筆に値する。
こうして目覚ましい発展を遂げてきた慶應義塾体育会も、昭和10年代後半には戦争激化のため衰退。学徒動員が行われた昭和18年には、出陣学徒壮行の早慶野球試合、いわゆる「最後の早慶戦」が行われ、期せずして尚校応援団から盛り上がった「海行かば」の厳粛な歌声とともに、体育会は明治25年以来の長く輝かしい歴史を一時中断し、平和の到来を 俟つことになった。
こうした状況の中、明治25年5月、柔道・剣道・野球・端艇・弓術・操練・徒歩の7部を組織的に統一する「慶應義塾体育会」が創立された。このときの評議員全記録には、体育会について「是迄の春秋運動会費を此倶楽部に給与して、春秋弐回の運動会を催さしむる事」とあり、当時の塾内におけるその役割を知ることができる。当時、「運動会」という言葉は今日より広義に使われており、遠足会なども運動会と呼ばれていた。義塾で初めて"運動会〟が開かれたのは明治16~17年という記録もあるが、今日いう意味での運動会は明治19年6月6日、三田山上の運動場で開催されたものが最初だったようである。その後、「慶應の運動会」は東京の市民の間で評判となり、明治28年には一万人の見物人を数えるほどとなった。
体育会では、その後も新たなスポーツが導入され、テニス、水泳、ラグビーなどの各部が創部された。明治36年には早慶野球戦が開始され、39年、両校学生の応援が過熱するあまり試合が中止されるまでになった。大正期に入ると体育会はますます発展し、14部を擁するに至った。このころ、各部の技術は著しく向上し、対外的に華々しい活躍を繰り広げていた。中でも、昭和期にかけて数度にわたりオリンピック大会へ塾生・塾員選手を送リ出したことは、特筆に値する。
こうして目覚ましい発展を遂げてきた慶應義塾体育会も、昭和10年代後半には戦争激化のため衰退。学徒動員が行われた昭和18年には、出陣学徒壮行の早慶野球試合、いわゆる「最後の早慶戦」が行われ、期せずして尚校応援団から盛り上がった「海行かば」の厳粛な歌声とともに、体育会は明治25年以来の長く輝かしい歴史を一時中断し、平和の到来を 俟つことになった。

<1>三田山上での野球(サード平沼亮三、ライト高石真五郎など)
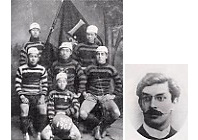
<2>ラグビー紹介者クラーク(E.B.Clarke)と部員たち

<3>学徒出陣の早慶戦、“海行くかば”を斉唱する慶應ナイン

<4>部下名物義塾運動会の図(「風俗画法」)

<5>福澤をかこむ剣道部員
体育会略年表
| 明治4年(1871) | ●三田山上に移転。在学生323名 |
|---|---|
| 明治17年(1884) | ●アメリカ人ストマーより塾生はじめて野球の指導を受く。 |
| 明治19年(1886) | ●三田山上で、はじめて陸上運動会を開催。 |
| 明治21年(1888) | ●三田ベースボール倶楽部組織。 |
| 明治25年(1892) | ●体育会創設。 |
| 明治32年(1899) | ●教員クラーク指導により日本ではじめてのラグビー競技行なわる(34年12月7日、横浜の外国人と日本初の試合を行なう)。 |
| 明治34年(1901) | ●外国人のボクシングを塾生にはじめて紹介。 |
| 明治37年(1904) | ●綱町運動場に柔道部、剣道部、弓道部の道場、兵器室および器械体操部練習場等竣工。 |
| 明治39年(1906) | ●早慶野球試合11月11日の決勝戦を中止。以後、大正14年秋まで行なわれず。 ●イギリス人牧師W.Tグレー来塾し、はじめてホッケーの技術を説明。 |
| 明治41年(1908) | ●野球部ハワイ遠征。 |
| 明治44年(1911) | ●第三高等学校との蹴球(ラグビー)試合。日本最初の蹴球対抗試合。 |
| 大正9年(1920) | ●第7回オリンピック大会(アントワープ)、熊谷一弥(テニス)、益田弘(陸上)出場。 |
| 大正13年(1924) | ●第8回オリンピック大会(パリ)、原田武一(テニス)、益田弘(陸上)出場。 |
| 大正14年(1925) | ●ラグビー蹴球部わが国最初の海外(上海)遠征。 |
| 昭和3年(1928) | ●山中山荘、各競技場および宿舎の一部が完成。 ●第8回オリンピック大会(アムステルダム)、三木義雄、津田晴一郎(陸上)、野田一雄(水泳)出場。 ●野球部、東京6大学リーグ戦に完全優勝(10戦10勝)を記念してストッキングに白線一本を加う。 |
| 昭和7年(1932) | ●第10回オリンピック大会(ロスアンゼルス)、役員、選手28名参加。平沼亮三団長。 |
| 昭和9年(1934) | ●日吉競技場開場。 |
| 昭和11年(1936) | ●第11回オリンピック大会(ベルリン)、役員、選手28名参加。平沼亮三団長。 |
| 昭和16年(1941) | ●他府県での合宿、試合は禁止された。(全国大会は明治神宮大会のみ)。 |
| 昭和18年(1943) | ●出陣学徒壮行早慶野球試合を早大戸塚野球場にて挙行。 ●スポーツ団体衰退し、対校競技はほとんど行なわれず。 |